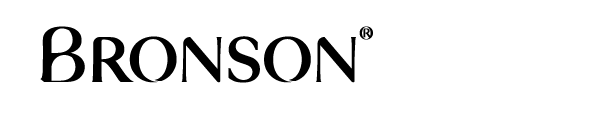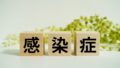朝食は1日3回の食事の中でも最も重要といわれていますが、どうやら骨の健康を維持するためにも大切なようです。
奈良県立医科大学の研究グループは、朝食を抜く人は骨粗鬆症による骨折リスクが高いことを報告しています。
この研究成果は、8月28日付のJournal of the Endocrine Society誌に記載されています。
なぜ朝食が大切なのか?
朝食とは、睡眠から目覚めて朝、最初にとる食事のことです。
現代では「1日3食」が当たり前ですが、実は歴史的には古いものではありません。
江戸時代中期(1650〜1750年頃)までは1日2食が一般的で、菜種油による照明の普及や外食文化の発展をきっかけに活動時間が延び、3食習慣が定着していったのです。
朝食は、体にスイッチを入れて活動を始めるエネルギー源、昼食で栄養を補充し、夕食で体を休める。
こうしてリズムが整うことで、心身の健康が維持されます。特に朝食は「1日の始まりをつくる重要な食事」といえます。
食物繊維も100gあたり4.1gとサツマイモの3.8gを上回り、特にワタの部分には果肉の約5倍程度も含まれています。

92万7130人を解析した大規模研究
研究グループは、2014〜2022年に健康診断を受診した20歳以上の92万7130人(中央値66.6歳、男性45.3%、女性54.7%)を解析しました。
対象者に骨粗鬆症の既往はなく、食習慣については問診票で確認されています。
その後、骨粗鬆症性骨折(股関節、前腕部、脊椎、上腕骨)との関連を追跡調査したところ、中央値2.6年で2万8196件の骨折が発生(1000人を1年間追うと約10.8人)。
解析の結果、
- 朝食を欠食した人は、骨粗鬆症による骨折リスクが18%上昇
- 遅い夕食をとる人は、骨折リスクが8%上昇
- 両方の習慣がある人は、骨折リスクが8%上昇
という結果が示されました。
さらに喫煙、毎日の飲酒、運動不足や睡眠不足もリスクを高める一方、十分な休養や速い歩行速度は骨折リスクを下げる要因となっていました。
朝食の研究報告は他にも
骨だけでなく、朝食習慣は全身の健康と深く関わっています。
例えば、
- 朝食の欠食は、肥満や糖尿病、腸内環境、認知機能低下、運動パフォーマンスの低下に関連する可能性(Nutr Res. 2025 Sep:141:34-45. doi: 10.1016)
- 朝食の欠食は、うつ病や注意欠如・多動症(ADHD)、認知機能低下、フレイル(虚弱)のリスクが増加(BMC Psychiatry. 2024 Apr 2;24:252.)
- 朝食の欠食は、心血管疾患が21%、全死亡リスクが32%増加(J Cardiovasc Dev Dis. 2019 Aug 22;6(3):30.)
- 朝食の欠食は、肥満やメタボ、筋肉量の減少と関連(動物実験)(Br J Nutr 2022 Dec 28;128(12):2308-2319.)
- 朝食をとると睡眠の質が高まり、寝つきも早くなる傾向(Curr Dev Nutr. 2018 Aug 28;2(11):nzy074.)
- 毎日朝食をとる子供は生活満足度が高い(Nutr J. 2024 Jul 16;23:78.)
つまり、「朝食を食べる」ことは「骨だけでなく心身全体を守る」ことにつながるといえると思います。

朝食を食べるメリット
最後に朝食をとることで期待できるメリットを6つにまとめました。
●脳と体のエネルギー補給
寝ている間に消費されたエネルギーを補充し、脳の働きを活性化させます。午前中から集中力や記憶力を高め、仕事や勉強の効率を向上させます。
● 代謝アップと肥満予防
朝食をとることで胃腸が動き出し、体温が上昇して代謝が活発になります。これにより、日中のエネルギー消費が高まり、太りにくい体質へとつながります。
● 生活習慣病のリスク低減
朝食をとることで血糖値の安定を促します。これにより、肥満や糖尿病などの生活習慣病のリスクを低減します。
●体内時計のリセット
朝食を摂ることで、日中に活動し夜は休息するよう調整されている体内時計がリセットされます。そのため、生活リズムが整い、睡眠の質の向上にもつながります。
●便秘予防
朝食が胃腸を刺激して動きを活発にすることで、排便を促し、便秘の予防につながります。
●精神の安定
脳にエネルギーが供給され、血糖値が安定することで、気分の浮き沈みやイライラを防ぎ、精神的な安定につながります。
参考)
J Endocr Soc. 2025 Aug 28;9(9):bvaf127.
1日3食をそれぞれバランスよくとることは理想的ですが続けていくことはなかなか難しいことです。
ただ、朝食を工夫して取り入れると、骨折予防・生活習慣病予防・心身の安定につながることが期待できます。
まずは、無理のない範囲で毎日の朝食を変えてみましょう。
- このコラムで紹介した情報は、一般的な知識のみを目的としたものであり、栄養素の効果・効能を保証するものではありません。
- 専門的な医学的アドバイスや特定の病状に対する治療の代わりとはなりません。