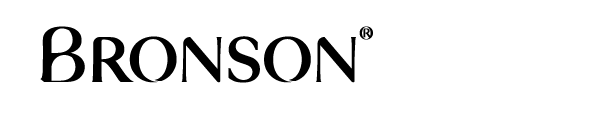私たちの身近な食品に含まれるフラボノイドという成分が、「健康寿命を延ばすカギ」になるかもしれません。
フラボノイドとは、植物に含まれるポリフェノールの一種で植物色素の総称です。
その種類は、4,000以上あるとされ、強い抗酸化作用や抗炎症作用を持つことが知られています。
例えば、緑茶に含まれるカテキンや赤ワイン・ブドウの皮に含まれるアントシアニンなどがフラボノイドに分類されます。
そして最新の研究により、「どのくらいの量を摂るか」だけでなく、「どれだけ多様な種類のフラボノイドを摂っているか」が、寿命や病気のリスクと密接に関係していることが明らかになりました。
この報告は、クイーンズ大学(英国)などの研究グループにより報告され、2025年6月2日号のNature Food誌に記載されています。
英国12万人を対象にした大規模研究
対象となったのは、UKバイオバンクに登録されている40歳以上の成人12万4805人。
対象者の食生活と健康状態を、平均10年間にわたって追跡調査したという信頼性の高い内容です。
UKバイオバンク:イギリス国内の40~69歳のボランティア約50万人を対象に健康・生活・遺伝情報を長期的に収集している大規模研究データベース。
これらのデータを解析した結果、以下のようなことが明らかとなりした。
最も多様な種類のフラボノイドを摂取していた人は、
- 死亡率が14%低下
- 2型糖尿病の発症リスクが20%低下
- 心疾患リスクが10%
- がん・呼吸器疾患リスクが8%低下

フラボノイドが豊富な食品は?
フラボノイドは、さまざまな植物性食品に含まれています。代表的なのは以下のような食品です。
- お茶(紅茶、緑茶、ウーロン茶)
- ベリー類(ブルーベリー、イチゴなど)
- 果物類(オレンジ、リンゴ、ブドウ、ミカンなど)
- 赤ワイン
- ダークチョコレート
- 大豆、タマネギ、ゴマ など
この調査の注目すべき点は、ある特定の食品からフラボノイドを摂ったとしてもその効果は限定的であったことです。
フラボノイドは多様な食品から摂ること
つまり、同じ500mgのフラボノイドを摂取していても、多様な食品から摂取した群の方が、単一または少数の食品から摂取した群よりも健康効果が高かったという点です。
言い換えれば、「摂取しているフラボノイドの種類の多さ」が重要ということです。
ある特定の食品から摂取するよりも、ベリー類やリンゴ、ミカン、ダークチョコレートなど、さまざまな食品を組み合わせて摂っていた人のほうが、健康面で明らかに良い結果を示しました。
フラボノイドの種類ごとの食材は、以下のような食材があります。
- イソフラボン:大豆、きなこ
- ケルセチン:.たまねぎ、りんご、エシャロット
- カテキン:緑茶、抹茶、小豆、ココア
- アントシアニン:赤ワイン、ブルーベリー、黒豆
- セサミン:ゴマ
- テアフラビン:紅茶
- ヘスペリジン:柚子、温州ミカン、レモン
- ルテオリン:ピーマン、春菊、セロリ
- ナリンギン:グレープフルーツ、はっさく
- タンニン:レンコン、緑茶 など
それぞれのフラボノイドには異なる働きがあり、組み合わせることで相乗効果が期待できるのとのこと。
また、フラボノイドには以下のような生理作用が知られています。
- 細胞の老化を防ぐ
- 炎症を抑える
- 血管の柔軟性を保つ
- 血圧上昇抑制作用
- 脂質低下作用
- 抗菌・抗ウイルス作用
- 炎症を抑える
- がん細胞の増殖を抑制する など

手軽にできる長生きの食習慣
フラボノイドは大豆や果物、野菜など、身近な食品に含まれており、特別なスーパーフードを用意しなくても手軽に摂取できます。
だからこそ、無理なく日々の食生活に取り入れることができます。
ただし、ビタミンCと同じ水溶性のため体内にとどまる時間が短く、一度にたくさん摂っても余分なものは排出されてしまいます。
そのため、「毎食ごとに少しずつ、同じ食材に偏らず、バランスよく摂ること」がポイント。
さまざまな野菜や果物をローテーションすることが、将来の健康と寿命にプラスに働くかもしれません。
参考)
Nat Food. 2025 Jun 2. doi: 10.1038/s43016-025-01176-1. Online ahead of print.
Medical xpress. June 3, 2025. edited by Lisa Lock, reviewed by Robert Egan
ルーラル電子図書館 農業技術辞典 フラボノイド
「食べたもので体はできている」とよくいいますが、フラボノイドの研究はそれを裏付ける科学的な証拠のひとつといえます。
健康を意識するなら、いろいろな食材を少しずつ楽しむことが、健康長寿への一歩につながります。
- このコラムで紹介した情報は、一般的な知識のみを目的としたものであり、栄養素の効果・効能を保証するものではありません。
- 専門的な医学的アドバイスや特定の病状に対する治療の代わりとはなりません。